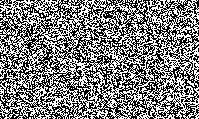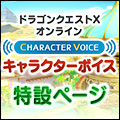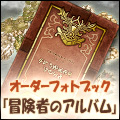アイリスの冒険日誌
2025-01-24 08:19:22.0 2025-01-24 09:16:40.0テーマ:その他
『〇〇が好きな人には〇〇な人が多い』
テーマ「〇〇が好きな人には〇〇な人が多い」:多様性と共通性の考察
「〇〇が好きな人には〇〇な人が多い」というテーマは、人間行動の興味深い側面を捉え、様々な角度から分析することができる。
【多様性(十人十色)】
趣味嗜好の多様性: 人はそれぞれ異なる価値観や経験を持ち、その結果、多種多様な趣味嗜好を持つことになる。
個人の複雑性: 人の好みは、単一の要因ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って形成される。そのため、一概に「〇〇が好き=〇〇な人」と断定することは難しいケースも多々ある。
【共通性】
社会的なカテゴリー: 特定の趣味嗜好を持つ人々は、ある程度の社会的なカテゴリーを形成することがある。例えば、音楽のジャンルやスポーツの種類、特定のブランドなど。
心理的な共通点: 共通の趣味を持つ人々は、心理的な共通点を持つ可能性も高いです。例えば、特定の価値観を共有していたり、似たような性格を持っている場合もある。
「入れ墨」を例に挙げた場合、上記の共通性の側面を顕著に示す例と言える。
歴史的・文化的背景: 入れ墨は、歴史的・文化的に様々な意味を持ってきてる中で、例えば、一部の文化圏では、入れ墨は社会的地位や所属を示すものであったり、宗教的な意味を持っていたりする中で、 現代社会においては、入れ墨は自己表現の一つの手段として捉えられることが多くなってきてる。しかし、一方で、入れ墨に対して否定的な偏見を持つ人もまだまだ少なくない。
共通する属性: 入れ墨を入れている人々には、必ずしも共通する属性があるわけではないが、反社会的勢力との関連性や、身体改造への興味といった共通点を持つ人もいる。
分類の難しさ:
「〇〇が好きな人には〇〇な人が多い」という関係性を分類することは、必ずしも簡単ではなく、下記の通り。
相関関係と因果関係: 二つの事象の間には、相関関係がある場合と、因果関係がある場合がある。例えば、特定の音楽を好む人と、ある特定の性格 traits が関連している場合、それは単なる相関関係かもしれないし、音楽が性格に影響を与えている可能性も考えられる。
多様な要因: 人間の行動は、様々な要因によって影響を受ける。そのため、一つの要因だけで、その人の性格や行動を完全に説明することはできない。
これを踏まえた上で、このゲームの種族についても「共通性」があって、
例えば、プクリポ。リアル高齢者が選ぶ最も多い種族と捉えていて、人を惹きつける為(要は第一印象)に選んでるケースが多い印象。逆に、年齢問わず異性を引き付けたいって人はウェディを選択している印象。特にバトル系にいるプク♂は高齢者がかなりの割合を占めている印象。
こういう分析は偏見にもつながるリスクを秘めていることから慎重さは必要だけど、その対象となるプレイヤーの言動などからある程度推測もできて、関わり合いを持つってテーマを考えるうえで必要な部分にもなるってこと。
おまけ
【バイアスから推測する年齢】
高い年齢の人のバイアスの特徴は、自身が認識していることが全てと信じ込み、バックボーンとなる根拠もそれなりに深い。
低い年齢の人のバイアスの特徴は、拾ってきた知識によるものが大半で、根拠が薄っぺらい。
「〇〇が好きな人には〇〇な人が多い」というテーマは、人間行動の興味深い側面を捉え、様々な角度から分析することができる。
【多様性(十人十色)】
趣味嗜好の多様性: 人はそれぞれ異なる価値観や経験を持ち、その結果、多種多様な趣味嗜好を持つことになる。
個人の複雑性: 人の好みは、単一の要因ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って形成される。そのため、一概に「〇〇が好き=〇〇な人」と断定することは難しいケースも多々ある。
【共通性】
社会的なカテゴリー: 特定の趣味嗜好を持つ人々は、ある程度の社会的なカテゴリーを形成することがある。例えば、音楽のジャンルやスポーツの種類、特定のブランドなど。
心理的な共通点: 共通の趣味を持つ人々は、心理的な共通点を持つ可能性も高いです。例えば、特定の価値観を共有していたり、似たような性格を持っている場合もある。
「入れ墨」を例に挙げた場合、上記の共通性の側面を顕著に示す例と言える。
歴史的・文化的背景: 入れ墨は、歴史的・文化的に様々な意味を持ってきてる中で、例えば、一部の文化圏では、入れ墨は社会的地位や所属を示すものであったり、宗教的な意味を持っていたりする中で、 現代社会においては、入れ墨は自己表現の一つの手段として捉えられることが多くなってきてる。しかし、一方で、入れ墨に対して否定的な偏見を持つ人もまだまだ少なくない。
共通する属性: 入れ墨を入れている人々には、必ずしも共通する属性があるわけではないが、反社会的勢力との関連性や、身体改造への興味といった共通点を持つ人もいる。
分類の難しさ:
「〇〇が好きな人には〇〇な人が多い」という関係性を分類することは、必ずしも簡単ではなく、下記の通り。
相関関係と因果関係: 二つの事象の間には、相関関係がある場合と、因果関係がある場合がある。例えば、特定の音楽を好む人と、ある特定の性格 traits が関連している場合、それは単なる相関関係かもしれないし、音楽が性格に影響を与えている可能性も考えられる。
多様な要因: 人間の行動は、様々な要因によって影響を受ける。そのため、一つの要因だけで、その人の性格や行動を完全に説明することはできない。
これを踏まえた上で、このゲームの種族についても「共通性」があって、
例えば、プクリポ。リアル高齢者が選ぶ最も多い種族と捉えていて、人を惹きつける為(要は第一印象)に選んでるケースが多い印象。逆に、年齢問わず異性を引き付けたいって人はウェディを選択している印象。特にバトル系にいるプク♂は高齢者がかなりの割合を占めている印象。
こういう分析は偏見にもつながるリスクを秘めていることから慎重さは必要だけど、その対象となるプレイヤーの言動などからある程度推測もできて、関わり合いを持つってテーマを考えるうえで必要な部分にもなるってこと。
おまけ
【バイアスから推測する年齢】
高い年齢の人のバイアスの特徴は、自身が認識していることが全てと信じ込み、バックボーンとなる根拠もそれなりに深い。
低い年齢の人のバイアスの特徴は、拾ってきた知識によるものが大半で、根拠が薄っぺらい。
いいね! 1 件