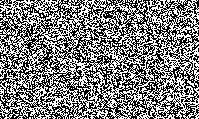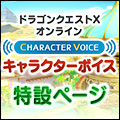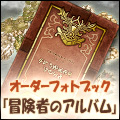ミラージュの冒険日誌
2015-02-15 13:53:00.0 2015-02-15 14:12:48.0テーマ:その他
なりきり冒険日誌~川の流れのように(2)
釣竿を握る手を緩めてページをめくる。次から次へとリーリナが情報をレポートする。
嬉しい報せはいくつもあるが、やはり目玉は各職業や武器の達人から聞き出したという新たな技能のことだろう。
魔法戦士団でも部外秘となっていた噂の新技能がまさかマダンテだったとは、私も驚きを隠せない。
古くは魔法都市カルベローナの大魔道士だけが扱えたという伝説の大呪文が使えるとあっては嬉しからぬ筈もない。
だが、扱い方はかなり難しそうだ。
記事に登場する魔法戦士うんにょも氏がどの程度の魔法力を秘めていたのかは不明だが、見たところ、破壊力は力を最大限に溜めた武闘家による棍閃殺より若干劣る程度か。魔法戦士の攻撃手段としては破格だが、戦局を決定づけるほどの一撃ではない。使った後のことを考える必要がありそうだ。
誰もが考えるのが、マジックルーレットとの併用。これならばすぐに魔法力を回復できる。が、しかし。いつ来るかわからないルーレットに頼るとなると、滅多に撃つことはできないことになる。
さらに言えば、その時が来るまでずっと杖を装備して魔法力を温存していたのでは、剣や弓による攻撃参加もできなくなってしまう。これでは本末転倒だ。
だが、このマダンテ。記事をよく見ると使用後に魔法力が徐々に回復する効果があるように見える。
で、あれば……
魔法戦士の戦い方は、MPパサーとギガスラッシュを除けば、それほど魔法力を消費するものではない。杖をもって戦闘を開始し、補助呪文とフォース、フォースブレイクを使ったら、思い切ってマダンテを打ち込んでみるのも一つの手段か。魔物の使うものと同じであればマダンテが放つのは光のエネルギー。フォースブレイクによるダメージ増加も見込める。
その後、杖から剣に切り替え、超隼斬り、隼斬りと連携をつないでいく。回復する魔法力が僅かなものであっても、この二つの剣技は魔法力をほとんど必要としないという地味な長所がある。そして魔法戦士の証の力で、さらに魔法力は回復していく。しばらく戦ううちに、バイキルトやピオリムを使うだけの魔法力は取り戻せるだろう。全てが理屈通りにいくかどうかはともかく、試してみる価値はある。
そしてもう一つ、忘れてはいけないのがシャイニングボウに続く弓の奥義、ダークネスショットだ。
シャイニングにダークネスとは、奇書"機動武闘伝"に登場した武侠師弟を思い出させるネーミングだが……。放たれた矢が理力を狂わせ、光に対する抵抗を弱める、ライトフォースを使える魔法戦士にはありがたい技である。
フォースブレイク、そして勇者姫の剣技を連想させる技だが、彼女の技はフォースブレイクに比べると耐性を弱める効果が弱い。およそ半分程度だ。
ダークネスショットはどうなのか……蓋を開けてみてのお楽しみである。
効果が強力な反面、フォースの合わせ方は難しそうだ。
弱点に合わせたフォースからライトフォースに切り替えた上でこの技を撃ち、抵抗されて慌てて元のフォースに戻す……という無駄は避けたい。敵が光に強い場合は特に、だ。
この判断は、経験が必要になりそうだ。
マダンテの威力を上げるための杖、そのフォローに有効な剣、第二のフォースブレイクとなる可能性を秘めた弓。三者三様の進化を遂げられるかどうか。早くも新時代の魔法戦士の闘法に思いを馳せ……
「……ん?」
……と、空想にふける私をぐいぐいと引っ張る者がいた。現実に引き戻された私が見たのは、ピンと張った釣糸だった。慌てて竿を引く。どうやったかよくは覚えていないが、しばらく悪戦苦闘が続く。
果たして、激流の中から顔を出したのは、一匹の鯉だった。 鯉の滝登りという言葉はあるが、本当に滝のそばで釣れるとは……。
鯉の滝登りという言葉はあるが、本当に滝のそばで釣れるとは……。
ひょっとしたら立身出世を目指して邁進中だったのかもしれないが、滝を登る最中に餌に目がくらんでしまうようでは、どの道、大成は難しかっただろう。
ありがたく釣果として魚袋に納める。後で聞いた話によれば、真のレンダーシアでも、このあたりには鯉がいるそうだ。どうもこの世界は魚の分布も本物そっくりに作られているらしい。マデサゴーラも律儀なことだ。
ある程度釣果を上げたところで、いい時間となり、私は釣竿をしまって魔法の絨毯を取り出した。
山道を下り、セレドの町を目指す。
空は既に薄暗く、あちらの世界では光の河に包まれたダーマのシルエットが荘厳に浮かび上がる時刻だが、こちらではただ山影が夜空に溶け込むだけだ。
さて、あの子供たちはどうしているだろう。
そして、どうなるのだろう。
寒々と吹く風に逆らい、絨毯が空をゆく。襟もとを正す。一つ、ため息。
どこからともなく響く、美しい音色が私の耳ヒレを揺らしたのは、その時だった。
嬉しい報せはいくつもあるが、やはり目玉は各職業や武器の達人から聞き出したという新たな技能のことだろう。
魔法戦士団でも部外秘となっていた噂の新技能がまさかマダンテだったとは、私も驚きを隠せない。
古くは魔法都市カルベローナの大魔道士だけが扱えたという伝説の大呪文が使えるとあっては嬉しからぬ筈もない。
だが、扱い方はかなり難しそうだ。
記事に登場する魔法戦士うんにょも氏がどの程度の魔法力を秘めていたのかは不明だが、見たところ、破壊力は力を最大限に溜めた武闘家による棍閃殺より若干劣る程度か。魔法戦士の攻撃手段としては破格だが、戦局を決定づけるほどの一撃ではない。使った後のことを考える必要がありそうだ。
誰もが考えるのが、マジックルーレットとの併用。これならばすぐに魔法力を回復できる。が、しかし。いつ来るかわからないルーレットに頼るとなると、滅多に撃つことはできないことになる。
さらに言えば、その時が来るまでずっと杖を装備して魔法力を温存していたのでは、剣や弓による攻撃参加もできなくなってしまう。これでは本末転倒だ。
だが、このマダンテ。記事をよく見ると使用後に魔法力が徐々に回復する効果があるように見える。
で、あれば……
魔法戦士の戦い方は、MPパサーとギガスラッシュを除けば、それほど魔法力を消費するものではない。杖をもって戦闘を開始し、補助呪文とフォース、フォースブレイクを使ったら、思い切ってマダンテを打ち込んでみるのも一つの手段か。魔物の使うものと同じであればマダンテが放つのは光のエネルギー。フォースブレイクによるダメージ増加も見込める。
その後、杖から剣に切り替え、超隼斬り、隼斬りと連携をつないでいく。回復する魔法力が僅かなものであっても、この二つの剣技は魔法力をほとんど必要としないという地味な長所がある。そして魔法戦士の証の力で、さらに魔法力は回復していく。しばらく戦ううちに、バイキルトやピオリムを使うだけの魔法力は取り戻せるだろう。全てが理屈通りにいくかどうかはともかく、試してみる価値はある。
そしてもう一つ、忘れてはいけないのがシャイニングボウに続く弓の奥義、ダークネスショットだ。
シャイニングにダークネスとは、奇書"機動武闘伝"に登場した武侠師弟を思い出させるネーミングだが……。放たれた矢が理力を狂わせ、光に対する抵抗を弱める、ライトフォースを使える魔法戦士にはありがたい技である。
フォースブレイク、そして勇者姫の剣技を連想させる技だが、彼女の技はフォースブレイクに比べると耐性を弱める効果が弱い。およそ半分程度だ。
ダークネスショットはどうなのか……蓋を開けてみてのお楽しみである。
効果が強力な反面、フォースの合わせ方は難しそうだ。
弱点に合わせたフォースからライトフォースに切り替えた上でこの技を撃ち、抵抗されて慌てて元のフォースに戻す……という無駄は避けたい。敵が光に強い場合は特に、だ。
この判断は、経験が必要になりそうだ。
マダンテの威力を上げるための杖、そのフォローに有効な剣、第二のフォースブレイクとなる可能性を秘めた弓。三者三様の進化を遂げられるかどうか。早くも新時代の魔法戦士の闘法に思いを馳せ……
「……ん?」
……と、空想にふける私をぐいぐいと引っ張る者がいた。現実に引き戻された私が見たのは、ピンと張った釣糸だった。慌てて竿を引く。どうやったかよくは覚えていないが、しばらく悪戦苦闘が続く。
果たして、激流の中から顔を出したのは、一匹の鯉だった。
 鯉の滝登りという言葉はあるが、本当に滝のそばで釣れるとは……。
鯉の滝登りという言葉はあるが、本当に滝のそばで釣れるとは……。ひょっとしたら立身出世を目指して邁進中だったのかもしれないが、滝を登る最中に餌に目がくらんでしまうようでは、どの道、大成は難しかっただろう。
ありがたく釣果として魚袋に納める。後で聞いた話によれば、真のレンダーシアでも、このあたりには鯉がいるそうだ。どうもこの世界は魚の分布も本物そっくりに作られているらしい。マデサゴーラも律儀なことだ。
ある程度釣果を上げたところで、いい時間となり、私は釣竿をしまって魔法の絨毯を取り出した。
山道を下り、セレドの町を目指す。
空は既に薄暗く、あちらの世界では光の河に包まれたダーマのシルエットが荘厳に浮かび上がる時刻だが、こちらではただ山影が夜空に溶け込むだけだ。
さて、あの子供たちはどうしているだろう。
そして、どうなるのだろう。
寒々と吹く風に逆らい、絨毯が空をゆく。襟もとを正す。一つ、ため息。
どこからともなく響く、美しい音色が私の耳ヒレを揺らしたのは、その時だった。
いいね! 18 件