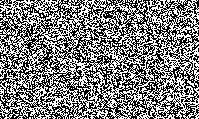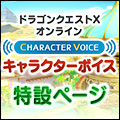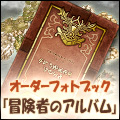ミラージュの冒険日誌
2016-12-27 22:44:08.0 テーマ:その他
海底散歩(1)~なりきり冒険日誌【ver3.4に関する記述有り】
 滑らかなラインを描いて流れていく魚群がカーテンのように水を区切り、絶対自由の深淵に形を与える。
滑らかなラインを描いて流れていく魚群がカーテンのように水を区切り、絶対自由の深淵に形を与える。深く深く、どこまでも続く海溝は、海という名の虚無である。
詩人たちの言葉を借りるなら、いつの時代も、果てしない虚空に意味と形を与てきたのは、脈打つ命の鼓動だった。
私は彼らほど気障なことを言うつもりはないが、海の底に次々と描かれていく自然の絵画を眺めていると少しも飽きることはなく、このままいくらでも時が過ぎてしまいそうだった。
あの日、ヒューザから様々な話を聞いた後、我々は再びオーフィーヌ海の探索に戻った。
聖塔を管理する青の騎士団とナドラガ教団の交渉は、どうやら膠着状態に陥っているようだ。状況を見守っていてもらちが明かない。
ならばこの隙に、オーフィーヌの各海域を調査させてもらおうというわけだ。
勿論、情報だけならルシュカの街でも色々と仕入れられるのだが、やはりこの足で歩き、この目で確かめたことに勝るものは無い。
例えば、オーフィーヌ海北東部、豊かの海に広がる海底花畑。
その名前から海中に花びらが舞うような美しい光景を想像していたのだが、訪れた我々を待っていたのは、薄暗い海底で不気味に息づく水中花の群れだった。
 一つ一つの花は美しいのだが、どうやら日当たりが悪いらしく、全て青白くくすんでしまっている。
一つ一つの花は美しいのだが、どうやら日当たりが悪いらしく、全て青白くくすんでしまっている。この暗さこそ風情というものではないか! と主張する者もいるだろうが、少なくとも私の感覚では、華のある景色とは思えなかった。
もっとも、海水の中で花を咲かせるこのデイジーが興味深い植物であることはは間違いない。私は植物学者ではないが、調査団への土産として何本か持ち帰ることにした。
周りには我々以外にも何人か、この花畑で花を摘む人々の影があった。ルシュカでは墓参りの際、この花を墓前に捧げる習慣があるそうだ。
そういう事情もあってか、人里離れた寂しい海底に佇む花たちはよりいっそう儚げに見えた。
◆
静かの海は、オーフィーヌ海の北西部。その名の通り穏やかな海である。
その平穏の源は、海流に身をゆだねて彷徨う、このドラゴンにあるという。
 ルシュカの民がリュウグウオウの名で呼ぶこの海竜は、この海域のヌシとして知られている。
ルシュカの民がリュウグウオウの名で呼ぶこの海竜は、この海域のヌシとして知られている。圧倒的体躯と威厳をもって海を支配する王が生物界の絶対強者として悠々と海底を闊歩し、他の魚たちは彼の邪魔をせぬようひっそりと岩陰を泳ぐ。
野生において、秩序とは絶対的な力によってのみ、もたらされるものなのである。
そんな秩序と肥沃な大地の元で悠々、平和を謳歌するのは、波間を漂うクラゲたちだった。
 半ば透き通った半透明のゼリーがぷかぷかと浮かぶ光景は何故か見るものを飽きさせず、奇妙なまでに心を和ませてくれる。
半ば透き通った半透明のゼリーがぷかぷかと浮かぶ光景は何故か見るものを飽きさせず、奇妙なまでに心を和ませてくれる。もっとも、癒されたいからと言ってあまり近づくのは得策ではないだろう。彼らは自らの平穏を乱すものを極端に嫌う。平和とは、平和の外側にあるものを排除することを意味するのである。
私もレーンの村で、遊泳中に何度か刺された経験がある。和みには程遠い体験だった。
こうした海と海を繋ぐのはいくつもの海底洞窟と、そこにうごめく溶岩の海である。海底火山に近づくと水温は上昇し、ちょっとした温泉気分となる。
ルシュカの人々もたまに遠出して温水浴を楽しむそうだ。
我々も久しぶりに汗をかき、自分の体温が冷え切っていないことにほっと胸をなでおろすのだった。
いいね! 8 件