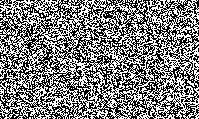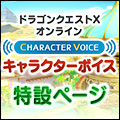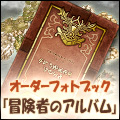ミラージュの冒険日誌
2020-08-15 21:01:13.0 テーマ:その他
竜は無慈悲な闇の帝王(3/4)~なりきり冒険日誌
挑戦は続く。

 レグナードとの戦いにおいて、魔法戦士である私の仕事は多い。
レグナードとの戦いにおいて、魔法戦士である私の仕事は多い。
敵のターゲットを見定め、自分とパラディン以外が狙いならばパラディンの隣に立ち、敵の侵攻を押し返す。
そして反撃を喰らわぬよう、一定のタイミングで離脱する。
クロックチャージで全員の動きを補助し、フォースブレイクでダメージを加速させる。
弓聖の守り星で降り注ぐ雷槌からパーティを守る。
怒りの闘気をまとったレグナードに対し、その行動を数え、ぎりぎりまで暴れさせたうえでロストアタックで鎮火する……この戦法の仔細は省くが、かなり特殊な戦い方だ。
そして咆哮への対処……状況によって前に出るか、下がるかを判断し、即決する。
その上で、隙を見て攻撃にも加わらなければならない。何しろ時間が足りないのだ。 私を最も悩ませたのは「黄色」以降の戦い方だった。
私を最も悩ませたのは「黄色」以降の戦い方だった。
レグナードは怒りの闘気を身にまとうと、必ずその直後に咆哮を放つ。鼓膜から心さえも貫き、冒険者の動きを封じる魔術的な雄叫びだ。
よほど離れなければ動きを封じられ、その場に倒れるこむことは免れない。だが問題は、どの位置で倒れるか、だ。
倒れていても壁の役目は果たせる。自分がターゲットでないなら、パラディンの隣で倒れて、一緒に壁とならねばならない。
そして攻撃役は魔法使いだから、怒りの矛先は常に魔法使いということになる。
要するにレグナードが怒った時、魔法戦士は必ずパラディンの近くで倒れていなければならないのだ。
もし後ろに下がった状態で倒れようものなら、パラディン一人では戦線を支えきれずにじりじりと追い込まれ……身動きの取れない魔法使いがまず暗黒の吐息に包まれる。続いて周囲を薙ぎ払う尾の一撃。おそらく、全滅だろう。
そう、前に出なければならない。
……だが、反撃に備えて、あるいは自分が狙われて、後ろに下がっている時に彼奴が怒り出したら……? 慌てて走ったところで間に合う距離ではない。
といって下がらずにいれば自分が倒され、戦線は崩壊する。お手上げだ。
私は答えを求めて先人の残した書物をあさった。
そして……そこに記されていた答えは、ロストアタックだった。 怒りのオーラを取り払う、鎮めの一撃。ロストアタックは多くの冒険者に愛用されている技である。
怒りのオーラを取り払う、鎮めの一撃。ロストアタックは多くの冒険者に愛用されている技である。
かつて、弓使いのロストアタックは失笑の的だった。何故、矢を飛ばさず弓で殴りに行くのか、と。確かに不自然にもほどがある。
だがこの場合、殴ることが重要となる。正確には、殴るための助走・突進の動作が。
殴りかかる勢いで一気に竜に接近し、打撃は当てずに寸止めする。これならかなりの距離を一瞬で詰めることができるだろう。意外な技が意外な局面で役に立つものである。
……とはいえ、これを読んだ当初の私は戸惑いを隠せなかった。
敵が怒りのオーラを纏ってから咆哮を放つ、そのわずかな時間に他の行動を中断し、ロストアタックに切り替えるなど、できるのか……? と。
できはしない。私は首を横に振った。
ならば、書物にかかれた戦術は机上論にすぎないのか?
そうではなかった。
切り替えることができないなら、最初から備えておくしかない。私はその日から、「黄色以降」で「敵が怒っていない場合」に敵から離れるときは、必ずロストアタックの構えを取りながら走ることにした。
反撃から逃れるとき、自分が狙われている時、常にロストアタックの構えだ。
……こうなると、ろくに他の行動がとれなくなる。私は、魔法戦士に許された自由時間が自分の認識よりよりずっと短いことを知った。クロックチャージや弓星の更新は、いつ行えばいい?
戦いの中で答えが出た。敵が怒っている最中だ。
怒っている相手がさらに怒ることはない。突然の怒りに怯えずに他の行動ができるわけだ。
奇妙な話だが、相手が怒り狂っている最中こそ、最も安全な時間だった。
逆に相手がなかなか怒らない場合は恐怖そのものである。特に、弓星を使うタイミングを作れないのが怖い。じっと我慢か、リスクを承知で使うべきか。悩ましいところだ。未だに答えは出ない。
それでも、レグナードが纏う恐怖のベールを一枚ずつ暴き、戦いのルールを理解していく過程は、ある種の歓喜を伴うものだった。
他のメンバーも、おそらくは似たようなものだったのではないか。
蝸牛の歩みとはいえ、我々は少しずつ前進していった。
そして、その日が来た。
(続く)

 レグナードとの戦いにおいて、魔法戦士である私の仕事は多い。
レグナードとの戦いにおいて、魔法戦士である私の仕事は多い。敵のターゲットを見定め、自分とパラディン以外が狙いならばパラディンの隣に立ち、敵の侵攻を押し返す。
そして反撃を喰らわぬよう、一定のタイミングで離脱する。
クロックチャージで全員の動きを補助し、フォースブレイクでダメージを加速させる。
弓聖の守り星で降り注ぐ雷槌からパーティを守る。
怒りの闘気をまとったレグナードに対し、その行動を数え、ぎりぎりまで暴れさせたうえでロストアタックで鎮火する……この戦法の仔細は省くが、かなり特殊な戦い方だ。
そして咆哮への対処……状況によって前に出るか、下がるかを判断し、即決する。
その上で、隙を見て攻撃にも加わらなければならない。何しろ時間が足りないのだ。
 私を最も悩ませたのは「黄色」以降の戦い方だった。
私を最も悩ませたのは「黄色」以降の戦い方だった。レグナードは怒りの闘気を身にまとうと、必ずその直後に咆哮を放つ。鼓膜から心さえも貫き、冒険者の動きを封じる魔術的な雄叫びだ。
よほど離れなければ動きを封じられ、その場に倒れるこむことは免れない。だが問題は、どの位置で倒れるか、だ。
倒れていても壁の役目は果たせる。自分がターゲットでないなら、パラディンの隣で倒れて、一緒に壁とならねばならない。
そして攻撃役は魔法使いだから、怒りの矛先は常に魔法使いということになる。
要するにレグナードが怒った時、魔法戦士は必ずパラディンの近くで倒れていなければならないのだ。
もし後ろに下がった状態で倒れようものなら、パラディン一人では戦線を支えきれずにじりじりと追い込まれ……身動きの取れない魔法使いがまず暗黒の吐息に包まれる。続いて周囲を薙ぎ払う尾の一撃。おそらく、全滅だろう。
そう、前に出なければならない。
……だが、反撃に備えて、あるいは自分が狙われて、後ろに下がっている時に彼奴が怒り出したら……? 慌てて走ったところで間に合う距離ではない。
といって下がらずにいれば自分が倒され、戦線は崩壊する。お手上げだ。
私は答えを求めて先人の残した書物をあさった。
そして……そこに記されていた答えは、ロストアタックだった。
 怒りのオーラを取り払う、鎮めの一撃。ロストアタックは多くの冒険者に愛用されている技である。
怒りのオーラを取り払う、鎮めの一撃。ロストアタックは多くの冒険者に愛用されている技である。かつて、弓使いのロストアタックは失笑の的だった。何故、矢を飛ばさず弓で殴りに行くのか、と。確かに不自然にもほどがある。
だがこの場合、殴ることが重要となる。正確には、殴るための助走・突進の動作が。
殴りかかる勢いで一気に竜に接近し、打撃は当てずに寸止めする。これならかなりの距離を一瞬で詰めることができるだろう。意外な技が意外な局面で役に立つものである。
……とはいえ、これを読んだ当初の私は戸惑いを隠せなかった。
敵が怒りのオーラを纏ってから咆哮を放つ、そのわずかな時間に他の行動を中断し、ロストアタックに切り替えるなど、できるのか……? と。
できはしない。私は首を横に振った。
ならば、書物にかかれた戦術は机上論にすぎないのか?
そうではなかった。
切り替えることができないなら、最初から備えておくしかない。私はその日から、「黄色以降」で「敵が怒っていない場合」に敵から離れるときは、必ずロストアタックの構えを取りながら走ることにした。
反撃から逃れるとき、自分が狙われている時、常にロストアタックの構えだ。
……こうなると、ろくに他の行動がとれなくなる。私は、魔法戦士に許された自由時間が自分の認識よりよりずっと短いことを知った。クロックチャージや弓星の更新は、いつ行えばいい?
戦いの中で答えが出た。敵が怒っている最中だ。
怒っている相手がさらに怒ることはない。突然の怒りに怯えずに他の行動ができるわけだ。
奇妙な話だが、相手が怒り狂っている最中こそ、最も安全な時間だった。
逆に相手がなかなか怒らない場合は恐怖そのものである。特に、弓星を使うタイミングを作れないのが怖い。じっと我慢か、リスクを承知で使うべきか。悩ましいところだ。未だに答えは出ない。
それでも、レグナードが纏う恐怖のベールを一枚ずつ暴き、戦いのルールを理解していく過程は、ある種の歓喜を伴うものだった。
他のメンバーも、おそらくは似たようなものだったのではないか。
蝸牛の歩みとはいえ、我々は少しずつ前進していった。
そして、その日が来た。
(続く)
いいね! 17 件